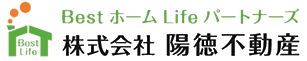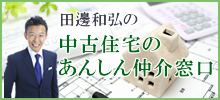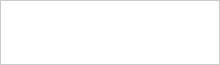| 遺言の形式 | 作成方法 | メリット | デメリット |
| 自筆証書遺言 | 日付、氏名を自筆の上押印。財産目録はパソコン作成可。 | 費用が掛からない。
手軽にすぐに書ける。 |
法的要件が不備の可能性。紛失や改ざんのリスク。家庭裁判所の検認が必要。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場に出向き公証人の前で口述し公証人が作成。承認が2名必要。 | 遺言として不備が無い。
原本は公証役場で保管のため改ざんされる可能性は低い。 |
費用が掛かる。証人が2名必要のため内容を完全に秘密にできない。 |
| 秘密証書遺言 | 作成した遺言書に署名、押印、封書にして公証役場に持参。承認立会いの下、遺言書を遺した事実を公証してもらう。原本は遺言者が保管。 | 内容を秘密にできる。 | 内容に法的不備があると無効の可能性。あまり活用されていない。 |
遺言書の形式は3つありますが秘密証書遺言は、ほとんど
実務で活用されることはありませんので実質、自筆証書遺言
と公正証書遺言の2通りになります。
公正証書遺言は費用が掛かりますが遺言者が公証人へ口述
した内容に従い公証人が作成するため法的不備がほぼありま
せん。遺言者の手が不自由で動かなかったり、しゃべれなかっ
たり、耳が聞こえなくても公証人が代わって書面を作成する
ので自分で書く必要がありません。
また、裁判所で遺言書の検認手続きも必要ありませんので速やか
に遺言書の内容を実行できるというメリットもあります。
対して自筆証書遺言の最大のリスクは自身が手書きで作成する
ため法的不備の可能性もあり、その場合は遺言としての機能を
果たさないことも考えられます。
また裁判所へ検認の申し立てという作業が必要になります。
検認とは相続人全員へ遺言の存在を知らせ遺言書の改ざんや
変造の防止を目的として行います。
そのため遺言書の内容を実行するまでには時間を要します。費用が
掛からないというメリットはあるものの法的要件の不備の可能性や
検認手続きがあることがデメリットになります。
しかし、民法改正に伴い自筆証書遺言の保管制度が新たに創設されました。
次回は自筆証書遺言保管制度についてお伝えしていきます。